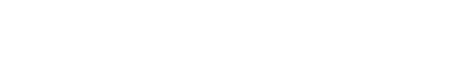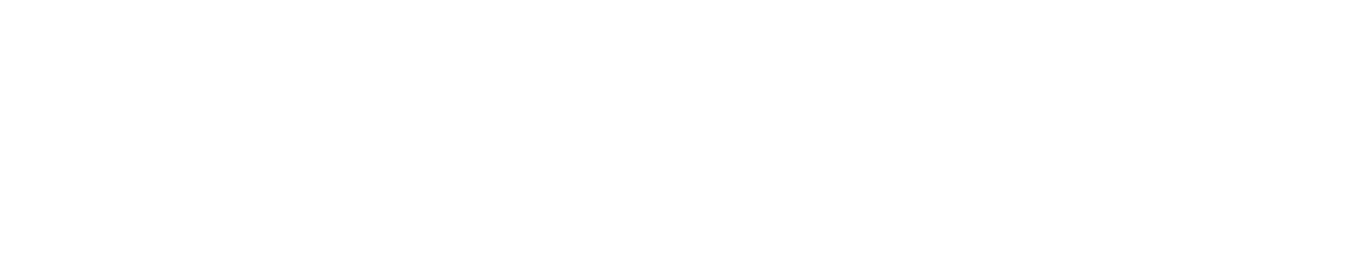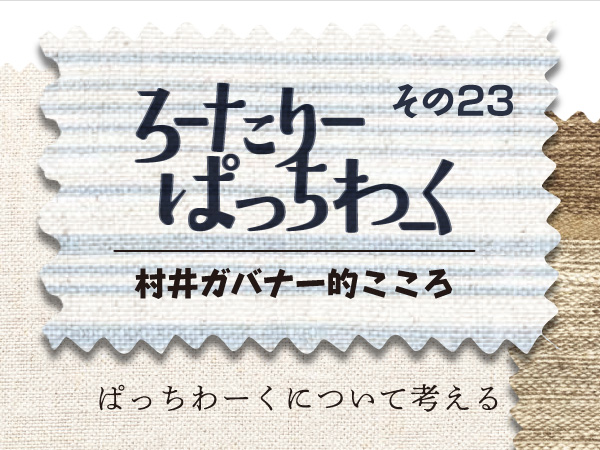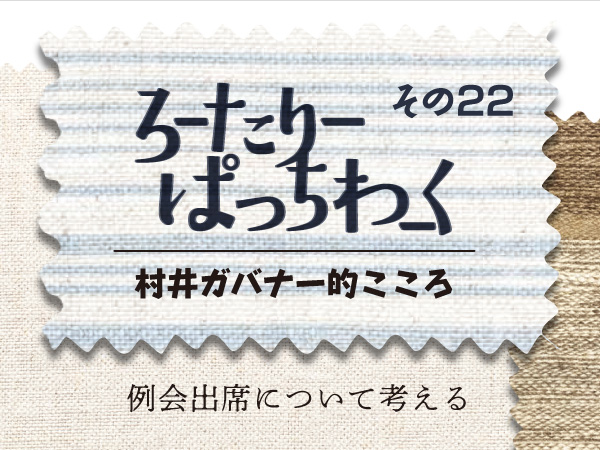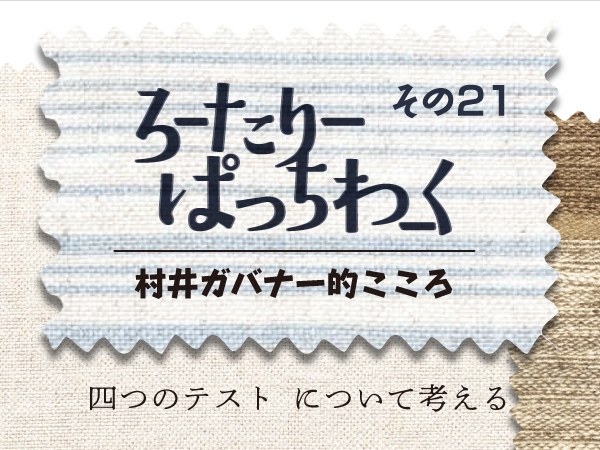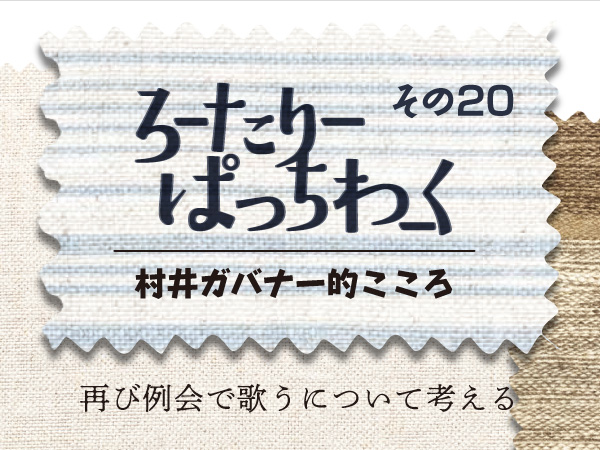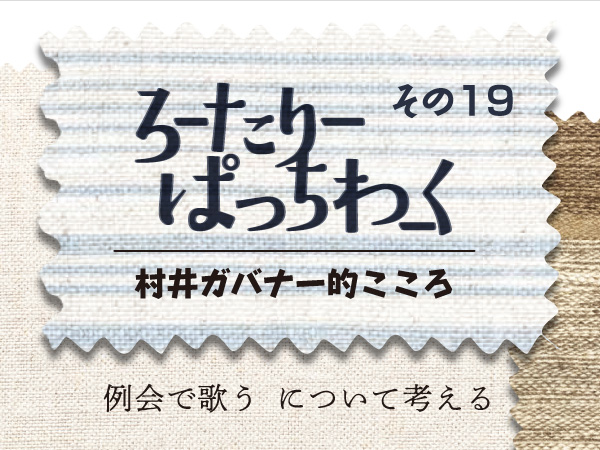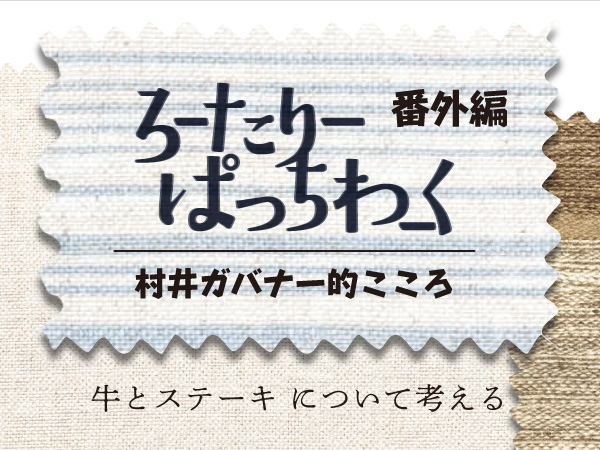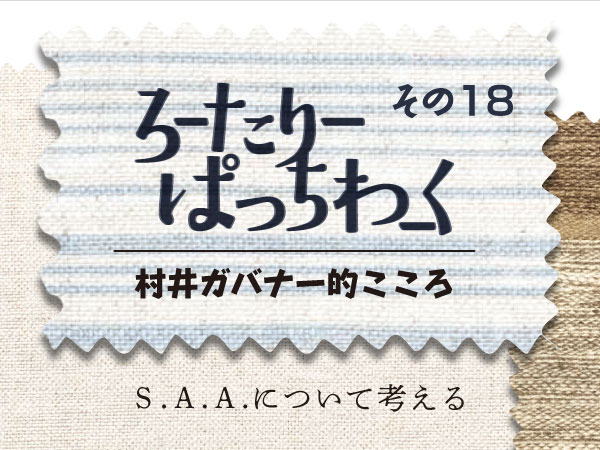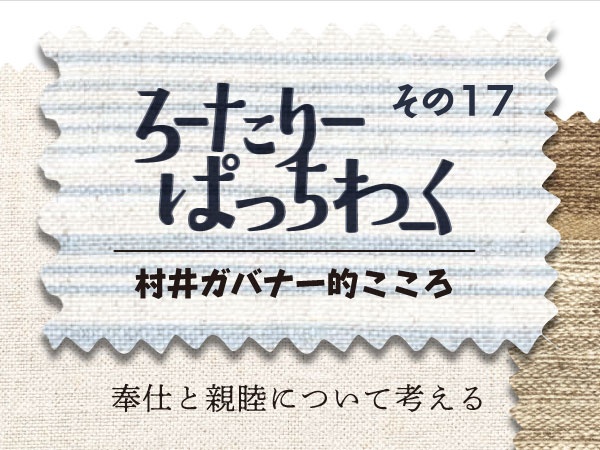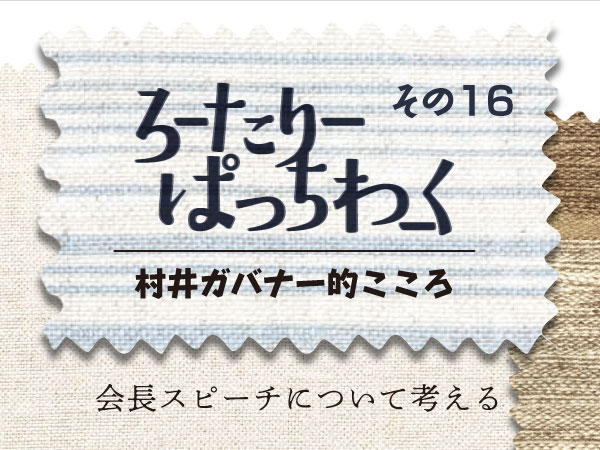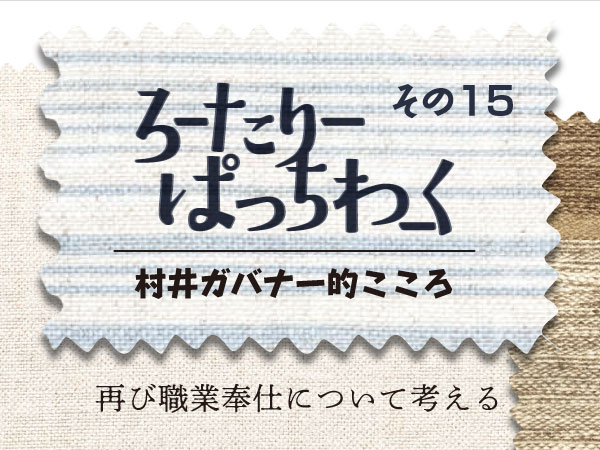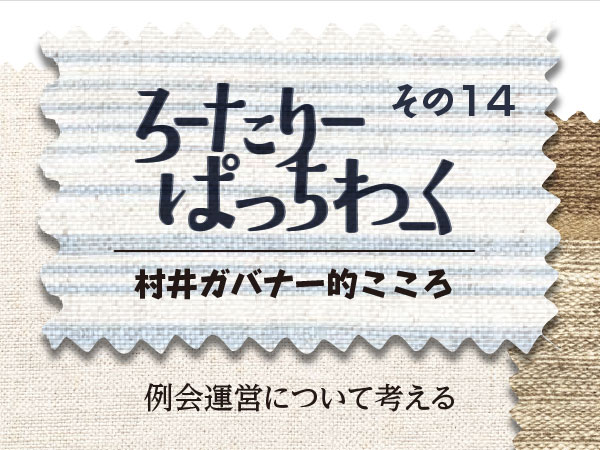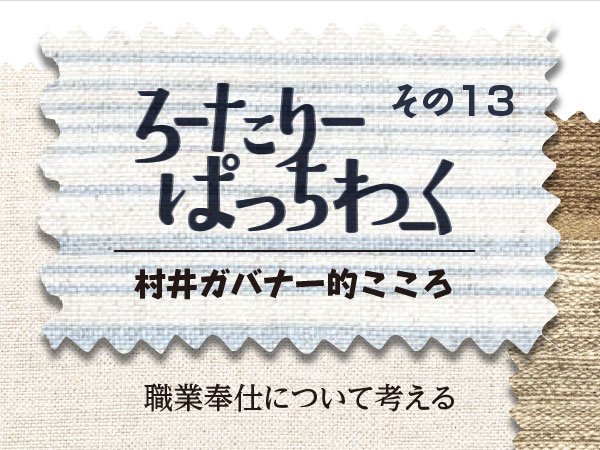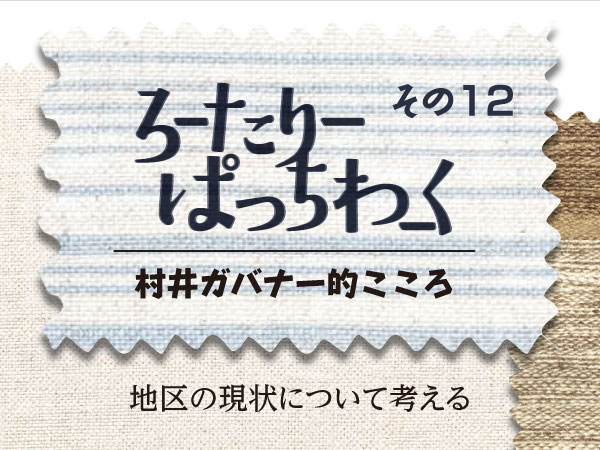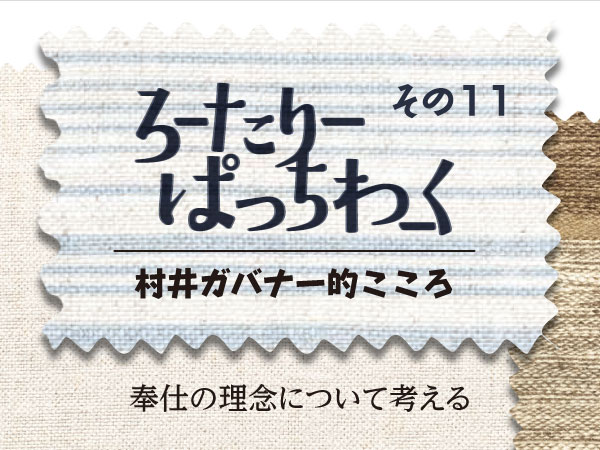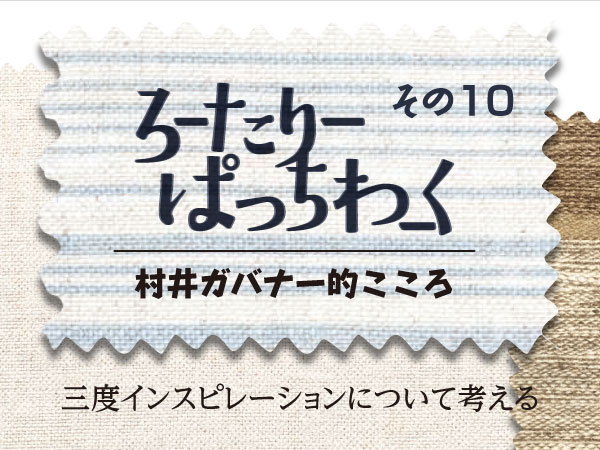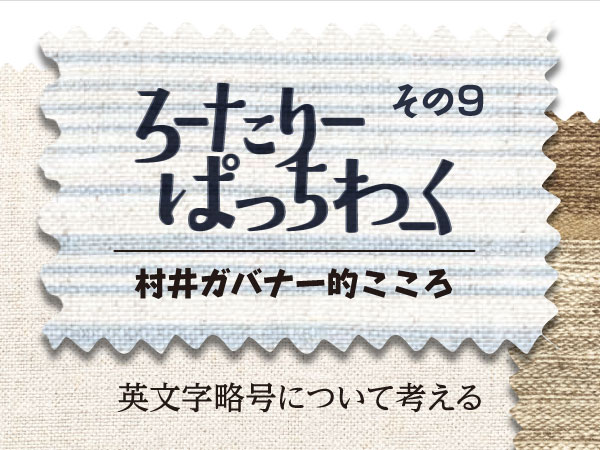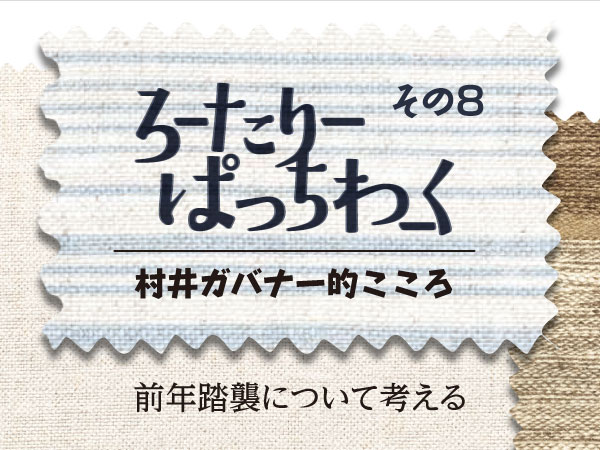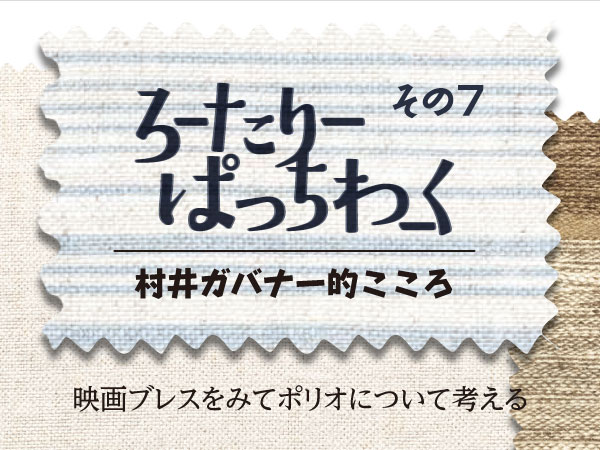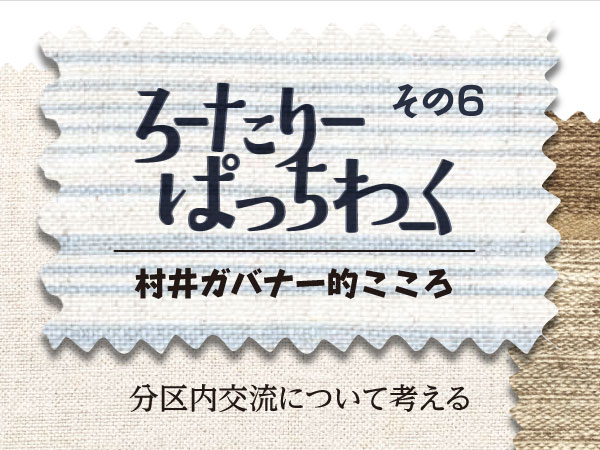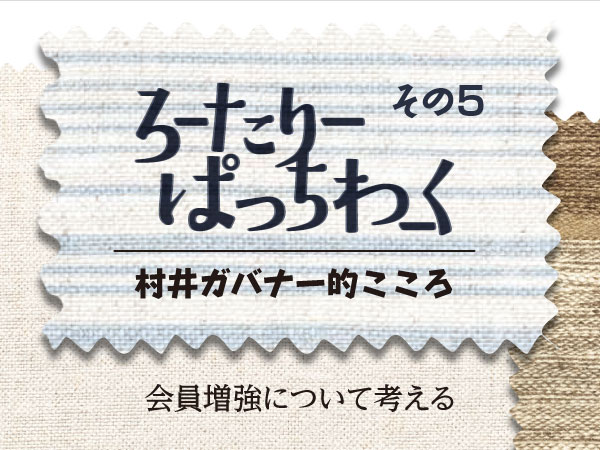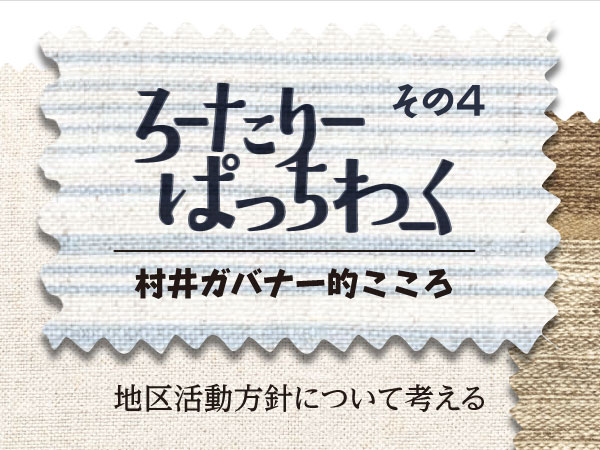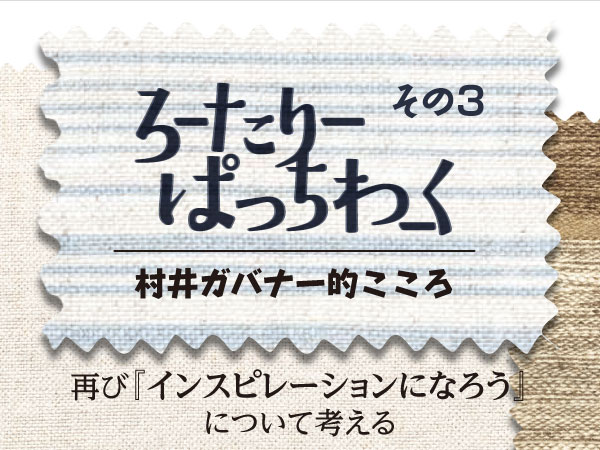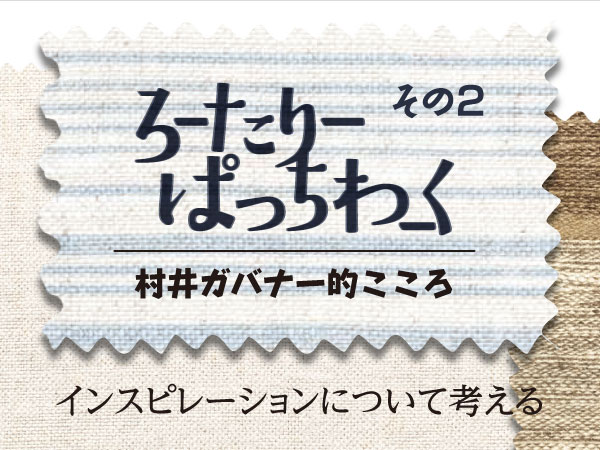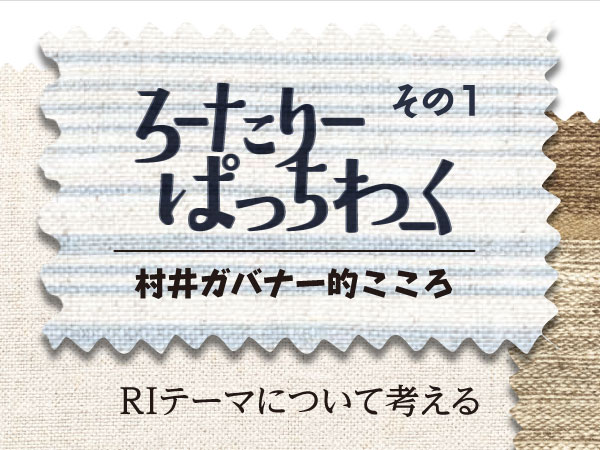2019年4月1日
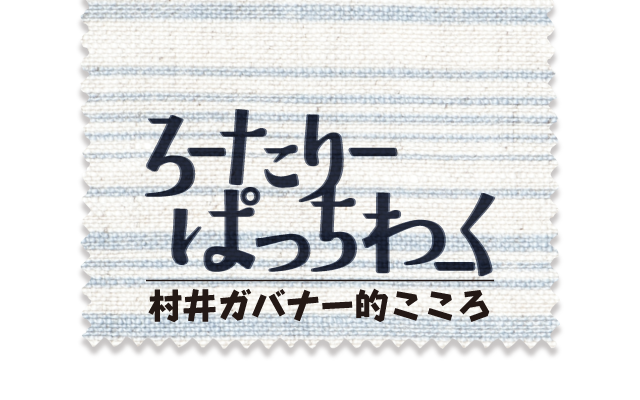
2019年4月1日
例会で歌う について考える
今回は例会で歌を歌うことについて考えてみる。
ロータリーの例会で歌を歌うことになったいきさつは、多くの会員がご存知だと思うので、ここでは簡単に説明しておくことにする。
ロータリーは既報の通り、シカゴで社交クラブとして発足した。しかし提唱者のポールハリスはカーターに入会を断られた時から奉仕に目覚めだした。しかしクラブの仲間は親睦と互恵取引のクラブだとして、ポールが奉仕の重要さを言えば言うほど反発が起き、クラブの中は、奉仕派と親睦派とは対立していった。
その時の会長ドクター・ネフは、ハリー・ラグルスという5番目にクラブに入会した会員にこう伝えたそうだ。『次の例会でポールはまた奉仕の重要さを言うだろう、そしてクラブの雰囲気はきっと悪くなる。そこで、君は歌がうまい、そうなった時には、君がリードして皆で歌を歌おうと、リードして欲しいと思うだが』と。
案の定、例会は気まずくなりかけた、その時ラグルスが椅子の上に立ち上がり、大きな声で『皆で歌を歌おう』と言った。これがロータリーの例会場で歌を歌う始まりだったといわれている。
したがって、懇親会の最後などで『手に手つないで』を歌う時には、遠慮されずにソングリーダーは椅子の上に上がってリードしてもらうのがよいと思っている。そして、ラグルスになった気持ちで、「さぁみんなで歌おう!!」と叫ぶのもよいと思う。
多くのクラブでは例会でロータリーソングを歌っている。私の所属クラブである豊橋RCでは、歌謡曲や抒情歌や童謡も歌っている。前述の通りでクラブの例会の雰囲気を和らげるのが目的であるから、楽しくにこやかに歌うことでよいので、曲目は何でもよいと思っている。公式訪問でほとんどがロータリーソングの「奉仕の理想」であったが、卓話講師やビジターとして訪問した時は、私のクラブと同じく歌謡曲などを歌うクラブをたまに見かける。
ロータリーソングについては、今年度2番や3番を歌ってほしいと地区運営方針でお願いした。残念ながら「奉仕の理想」は1番のみであるが、「我らの生業」は2番まで、「それでこそロータリー」は3番まである。当地区の地区大会に来られた同期のガバナー数名が、自分の地区大会で「我らの生業」を2番まで歌うことにされたそうだ。私はロータリーソングは、2番3番の歌詞を知ったほうが良いと思うし、ロータリーとして良い内容の歌詞だと思っている。
最近では創立の若いクラブなどでは「四つのテスト」「日も風も星も」などを歌うクラブも増えているが、歴史の長いクラブでは、これらの歌に馴染みがない会員も多いようだ。
国歌「君が代」を月初めなどに歌うクラブが多いし、地区行事では点鐘後、まず初めに「君が代」を歌う。この時に、指揮者が出てこられることが多いが、いかがなものであろうか。
本来国歌斉唱なので、国旗に向かって全員で歌えばよいので、国旗に向かうことなく、指揮者を向くのも変だと思っている。さらに国旗にお尻を向けての指揮もいかがなものかと思う。
「君が代」はほとんどが4分音符で指揮に合わせないと歌えないほどの難しい曲ではないであろう。伴奏を担当する演奏者に対しては必要なのかもしれないが、ほとんどがピアノ伴奏か録音された伴奏である。
ロータリー以外の行事にも出るが、「君が代」で指揮者はなく、前奏に引き続きとのアナウンスですますことが多いと思う。大相撲で土俵上に指揮者が現れて歌うなど、とても想像できないが、皆さんはどう思われるであろう。
ちょっと横道に逸れたが、例会の運営に欠かせない歌を歌う時間とは、やはり皆が楽しく過ごすためにすれば良いのではと思っている。
RID2760 2018-19 ガバナー 村井總一郎